公益社団法人全日本能率連盟(全能連、AFMO)は、2024年度『全能連マネジメント・アワード』を開催しました。より多様な業界・職種を対象とし、経営やマネジメントに関する革新的な支援活動や実践を行っている方々の業績を讃えて表彰します。
去る2024年1月24日に行われた第二次審査(発表会)において最優秀の「全能連マネジメント大賞」を受賞されたのは、渡邊 敬二氏(わたなべ行政書士事務所)の「実践型介護BCP」です。

◆この度は大賞受賞、おめでとうございます。まず、受賞の知らせを受けたときのお気持ちをお聞かせください。
渡邊:「以前より、全能連マネジメント・アワード大賞への関心を持っておりました。これまでの事業継続計画(BCP)の策定結果や研究を発表するいい機会でした。事務局より大賞受賞のご通知をいただいて喜びよりも驚きを、驚きよりも「私の研究が評価に値するのか」という思いがありました。やがて受賞から一カ月余ですがようやく実感が湧いております。」
◆今回、応募するきっかけとなったことはなんでしょうか。
渡邊:「BCPは施設・設備のインシデント対策がメインでありますが、同時に、海水温の上昇によるメガ台風の発生や地震・津波等、災害規模が広域化して事業所と同時に職員も被災するケースが発生しております。BCPの実践性を確実にするために従業員(職員)の生活上の事業継続(LCP・CCP)が重要であることに着目し、その研究成果の発表としてアワードへ応募しました。」
◆介護BCPを策定するにあたり、最初に着手したことや重要だと感じたステップについてお聞かせください。
渡邊:「最初にBCP研究を進めるため、いくつかの教科書を参照し、特に「経営戦略としての事業継続マネジメント」や「BCP策定ガイドライン」などの書籍を何度も読み返し、重要事項を確認しました。さらに、介護BCPに関しては、厚生労働省のガイドラインや過去の被災経験を参考にして、地元企業のBCP策定を実施し、その経験を介護BCPの基礎に活用しました。また、BCPの歴史的考察では、9.11アメリカ同時多発テロ後のBCP導入が一般的ですが、実際には1941年の真珠湾攻撃からミッドウェー海戦に至るまでの米国の対応がBCPの重要な要素となっていると考えました。特に、戦略対策や情報対策、後方支援、人員確保が重要だと気づきました。介護BCPにおいても、災害歴やハザードマップを参考にRTO(目標復旧時間)やRLO(目標復旧レベル)を策定し、備蓄や情報体制整備、人員確保といった戦略的な対策を講じることが重要だと認識しました。
◆BCP策定の中で、特に工夫した点や成功の要因はどのようなところにあったとお考えですか。
渡邊:介護事業のBCP策定における工夫は以下の点です:
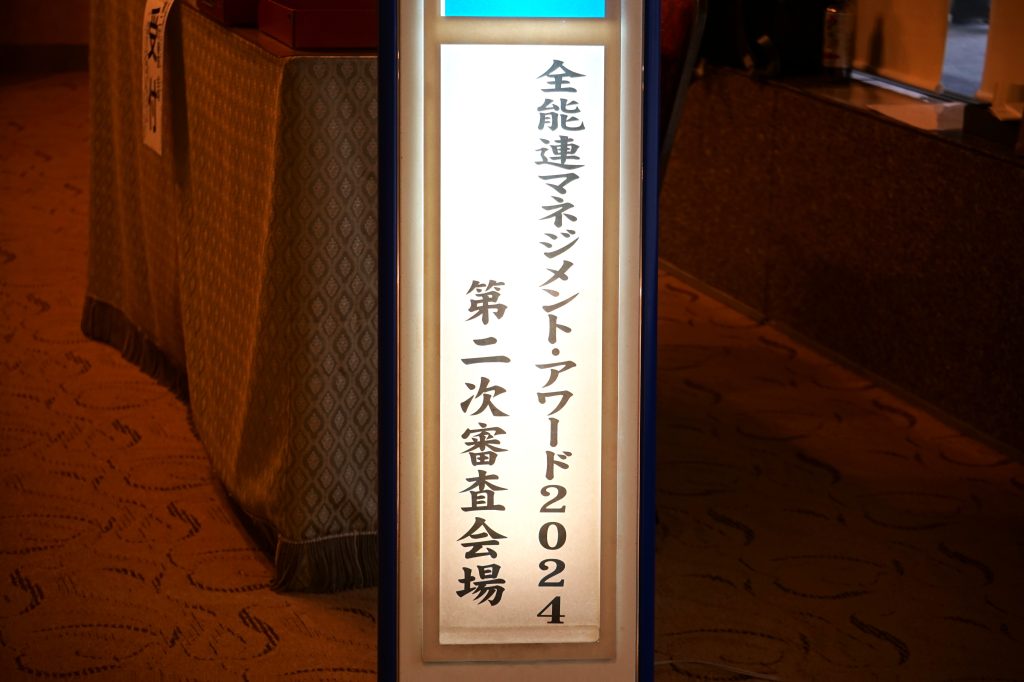
介護BCPの計画策定の成功要因は、実際の災害時に計画が機能するかどうかにかかっており、机上訓練での対応が問題なく行える点で成功していると考えています。これまで大阪府、兵庫県、愛媛県などの南海トラフ地震に備えたBCPを策定し、被災規模に合わせた対応をしていますが、広範な被災規模に対しては機能するかどうかの判断が難しいと感じています。また、感染症に対する対応は新型コロナウイルスや他の呼吸器系感染症には対応しているものの、気候変動に伴う新たな感染症への対策が不足しているため、完全な成功とは言い難いと考えています。これらを踏まえ、長期的な研究とインシデントへの対応策の検討が成功への鍵だと考えています。
◆BCP策定においては、他業界にとっても有益な要素が多く含まれているかと思います。他業界へ向けて何か発信すべきことがあればお聞かせください。
渡邊:「介護事業のBCP(事業継続計画)は、製造業とは異なり、製品や部品の生産ではなく、介護サービスの継続を目的としています。被災時にはサービスを受ける高齢者が影響を受けるため、BCPの目的は被災の影響を最小限に抑え、ライフラインの代替や備蓄を活用して早期の復興・復旧を実現することです。しかし、現在の介護BCPは完全には策定されていません。
BCPにおける重要な要素は、介護・看護・給食などの職員の確保です。広域的な災害で職員が被災すると事業継続が困難になるため、平成30年の研究会で提案された「LCP(従業員と家族の生活継続)」と「CCP(地域との相互扶助)」の概念を介護BCPの基本要件として採用しています。気候変動による災害の規模拡大を考慮し、従業員とその家族の生活の継続が事業継続の鍵となるため、今後のBCPにはLCPとCCPを組み込むことが重要だと考えています。」
◆渡邊様は行政書士またコンサルタントとしてご活躍されておりますが、なぜこの介護業界に携わることになったのかお聞かせください。
渡邊:「平成11年度に阿蘇地域介護認定審査会の事務局担当として介護保険事業全般を学び、平成18年度には特別養護老人ホーム施設管理者として介護事業の実践を経験しました。その後、介護BCPの策定に携わり、熊本地震後には「BCPくまもと研究会」を設立し、介護BCPの研究を行いました。令和2年の新型コロナウイルス蔓延時には、介護施設の孤立や職員不足などの問題を踏まえて、「BCP策定塾」を設立し、介護BCPの策定を支援しました。さらに、厚労省の介護BCP指示を受け、熊本県内の介護施設で実際に介護BCPを策定し、職員確保を最重要課題としてLCPCPを組み込んだ計画を完成させ、その成果を基に「介護BCP策定ガイド」を執筆・発刊しました。」
◆今後の介護BCP策定において、さらに注力したい点や新たに取り組みたい課題はありますか。
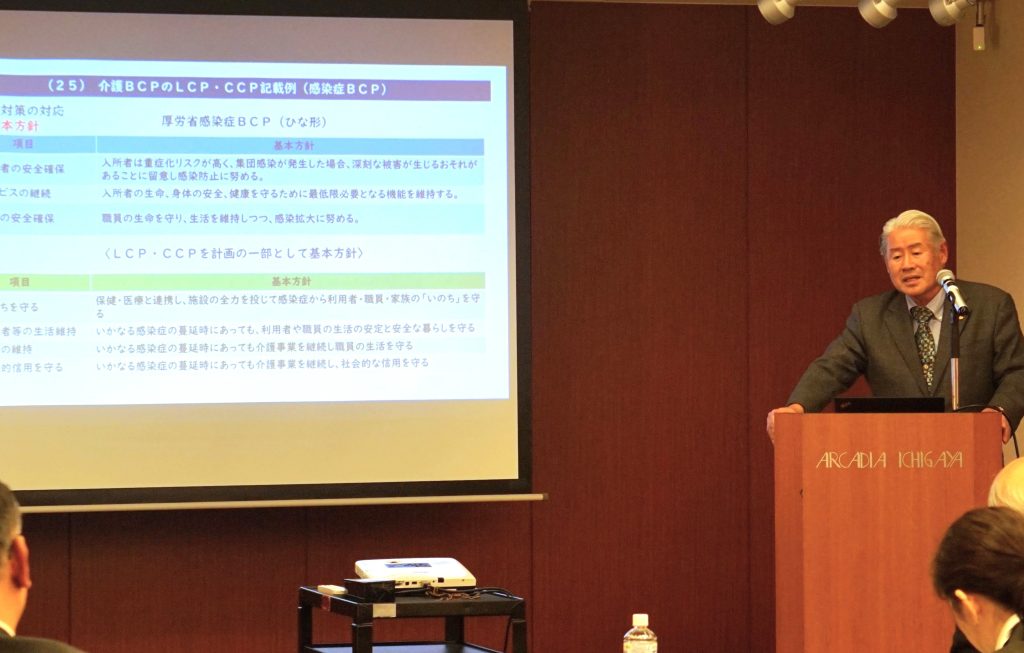
渡邊:「介護BCP(事業継続計画)は、災害や感染症の影響が高齢者の生命に直接関わるため、企業のBCPとは異なり、利用者の安全確保が最優先です。介護施設が被災した場合、長期間の休業が必要となり、高齢者の「災害関連死」や避難所での生活困難が懸念されます。訪問看護や介護では、避難所で生活する高齢者への支援や、通所介護の早期再開などが重要な対応になります。介護BCPは、自然災害や感染症に備えた高い実践性が求められ、実効性のある計画策定が課題となります。」
◆このアワード受賞がご自身の今後のキャリアや地域社会にどのような影響を与えるとお考えですか。
渡邊:「現在、行政書士として熊本県行政書士会に所属し、主に公的補助金申請や介護事業所の事業継続、研修業務に従事しています。熊本地震以降、罹災証明発行や補助金申請支援に力を入れており、介護BCP(事業継続計画)の策定にも関与しています。当初、BCP策定に対して疑問の声もありましたが、熊本県行政書士会は、BCPの策定が行政書士の業務に含まれると認識し、関心が高まりました。介護BCPの策定率が低い理由として、専門家の不足が指摘されており、大規模災害の予測に伴い、事業継続計画の需要が増すと考えられています。全能連マネジメント・アワードで大賞を受賞し、介護BCP策定への関心を喚起する意義があったと評価しています。」
◆これから応募する方にメッセージなどお願いします。

渡邊:「BCPの研究を進める友人に入賞を報告した際、在京、在阪ではない、九州、熊本という地方の研究者が受賞したこと、中堅大手のコンサルタント会社や大学の研究者でない研究者が受賞したことに驚きがあったようです。
また、経営研究では「事業継続計画」が研究のメインになることはなく、付属的な立場であったので驚いたようです。
これから応募する方へ、経営研究には表や裏、主流や反主流といった障壁はありません。また、理論もさることながら実践性を高く評価できるのも、新たな潮流と言えます。私が感じていた中央(在京・在阪)や組織や組織の規模等も検討するに値しない要件ではないでしょうか。
更に、経営研究には「気づき」という事が重要な要因ではないでしょうか、特に、市場規模の大小や国際性等の要件を求めますが、併せて実生活で与えられた課題を研究するのも重要です。 今後は全能連マネジメント・アワードを経営研究発表の最大チャンスとして、是非、挑戦してください。」
本アワードは、自分たちの思考プロセスが広く受け入れられるかどうかを確認することができる場であります。
◆◆ありがとうございました。今後の渡邊さんのご活躍を期待しています。◆◆
<渡邊 敬二氏プロフィール>
合同会社JMCA執行役員、一般社団法人日本経営調査士協会経営調査士、公益社団法人全日本能率連盟認定マネジメント・コンサルタント(J-CMC)、BCPアドバイザー、行政書士(熊本県行政書士会所属)。
1976年(昭和51年)福岡大学法学部卒業後に民間企業へ就職。企業を退職後、帰郷(熊本県阿蘇市)し、団体職員や公務員を経て2014年(平成26年)に定年退職。翌年「わたなべ行政書士事務所」を設立し現在に至る。
熊本地震(2016年発災)後の2018年(平成30年)には、くまもと型BCP策定やBCPの普及をめざし、事業継続計画(BCP)と深く関わることになる。以後、民間企業等の事業継続計画(BCP)等の策定やセミナーの開催によりBCPの普及に携わる。